過保護や過干渉は
子どもの行動や言動に対して
大人の理想や願望を押し付けて
○○しなさい、○○はダメ
と伝えてしまうことありませんか?
これらを続けてしまうと
子どもの将来の成長・性格形成
において大きな影響を
与えるものになります。
今回は
過保護の対応
過干渉の対応
をするとどのような
影響を受けるのかを見ていきます。
過保護と過干渉
過保護は
必要以上に子どもを甘やかす
子どもの願望を何でも叶えてしまうこと
過干渉は
行動を制限したり
無理やり考えを決めたりすることを
意味しています。
こうした対応や状態が
取られ続けると子どもに
どんな影響が出てくるのか
いくつか挙げていきます。
過保護と過干渉が与える影響
ずっと親の指示を受け続けた子どもは
指示がないとどのように動いたら良いのか
自分で判断が難しくなってしまう
自分で考えないで
誰かからの指示や教えてもらうことが
ないと動けないように
なってしまいます。
欲しいものを親が察して
言葉や態度にして求めなくても
すぐに与えられてきた子どもは
ハッキリとした要求を見せなくても
応えて貰えていた分
自分がどのように主張すれば良いのか
分からずに人間関係で躓いてしまう
ことがあります。
親に本当の気持ちを
伝えられなかった子どもは
自分がしたかったこと
してほしかったことを
親の顔色や様子をうかがう癖が
ついてしまうので
自分の気持ちを他人に伝えることが
苦手になってしまいます。
子どもが起こしたトラブルを
親が代わって解決してもらっていた子どもは
自ら問題に立ち向かうための勇気が持てず
方法が分からなくなってしまいます。
親や周りの誰かのせいにしたり
自分の行動に責任を持たずに
誰かが助けてくれるという頭
になってしまいます。
子どもの成長を促す上での大切な観点
子どもの成長を促す上で
大切な観点は
目先の問題に囚われずに
今の子どもがどうしているか、
ということ以上に
これから子どもが
成長した時にどうなっているか
どうなっていてほしいのか
先々の大きくなった時のことを
見据えた子育てが求められます。
自分が子どもに対して
していることの延長線上に
子どもの幸せがあるのか
を考えることが大切です。
「良い子」に育てたいという
親心はどんな親にでも
あると思います。
ですが、「良い子」とは
どういう子のことを
言うのでしょうか?
「良い子」とは?
親の言うことを素直に聞いて
問題を起こさない子どもですか?
本当にそうでしょうか?
それは、あくまで大人の視点で
今の時点では負担がなく
楽で助かるかもしれません。
子どもにとっては
我慢をしながら取っている
行動や言動かもしれないことを
忘れてはいけません。
将来の子どもになってほしい理想として
自分の気持ちをしっかり言えて、
自己主張が出来る子に
なってほしいと思うとします。
なのに手の掛かる年頃の時には
勝手なことをしないで言うことを聞きなさい
と伝えている、となると
子どもが成長をするにつれて
自分で考えなさい
自分の気持ちを伝えられるようになりなさい
と押し付けられても
子どもは困惑や不満を持ってしまいます。
過保護と過干渉のチェックリスト
以下は、過保護や過干渉的な行動についてのチェックリストです。
【過保護チェックリスト】
- 子どもが自分で問題を解決できるかどうかを常に心配している
- 子どもに対して、常に注意を払い、何かあればすぐに介入する
- 子どもに対して、常に助言や指示を与える
- 子どもが感情的になった場合に、すぐに解決策を提示する
- 子どもが自立的に行動することを妨げるような行動をとってしまう
- 子どもに対して、自分の代わりに決定を下そうとする
- 子どもに対して、過度に肯定的な評価や称賛を与える
【過干渉チェックリスト】
- 子どもの行動や意見に対して、常に口を出してしまう
- 子どもに対して、常に支配的な態度をとる
- 子どもに対して、常にやることを指示する
- 子どもに対して、自分の意見を押し付ける
- 子どもが自分で行動する機会を与えない
- 子どもが自分で考え、行動するための時間を与えない
- 子どもに対して、自分の判断や意見を尊重しない
過保護や過干渉的な行動は、子どもの自己決定能力や自信を損なうことがあります。親が子どもに対して適度な自由や責任を与えることは、子どもの成長にとって重要です。
「体験」や「経験」が大切
子どもにとって
「体験」や「経験」は
成長していく上で
大きな糧となります。
ですが、
親の視点や観点を押し付けて
子どもの考えや行動を指示してしまうと
「体験」から学ぶ機会を失ってしまいます。
子どもの「体験」や「経験」に
親(大人)の価値観を押し付けて
邪魔をしてしまうと
子ども自身の可能性を
ないものとしてしまうことがあるのです。
○○しなさい、○○したらダメと
制限を掛けるのではなく
大きくなった時に子どもが
困らないように
いろんな「体験」をさせつつ
自分で気付かせることを
子育ての中で意識すると
叱る質も変わってきますし
子ども自身も自分で考える力が
養われていきます。
子どもは無力ではない
子どもは出来ないことは多くとも
無力ではありません。
そして、大人が思っている以上に
心も体も成長が早いです。
世話を焼き過ぎるのは
子どものためになりません。
子どもの可能性を広げるためにも
「体験」や「経験」をさせる勇気を
持つことも大切です。
子どもに対してリスペクトの心を持つ
チェックリストをしてみて、いかがでしたでしょうか。
我が子への接し方で当てはまる点があったかもしれません。
過保護にしても過干渉にしても、子どものためを想って行っていることも多いかもしれません。
我が子に自分のエゴや固定概念を押し付けて、自由な思考や行動に制限するような関わりを
することは、自尊心やその子自身が持つ可能性を損なわせてしまうことになりかねません。
子どもに対して、口出しや助言をしてしたくなるのは、子どもが危険から守り、安全に成長してほしいという想いからだと思います。
しかし、子どもにも人権や尊厳がある一人の人間であることを忘れてはいけません。
子どもだからと言って、決めつけて口を出したり、介入をしてしまうのは、我が子に対して
リスペクトすることが出来ていないと言えます。
子どもの好奇心は、危険と隣り合わせなこともあります。
ですが、そうした経験や体験から良いこと、悪いことを学んでいき、自分の糧にしていきます。
興味や好奇心に対して、尊重して接することで
あなた自身が気付かされることや、ハッとさせられることもたくさん出てくるでしょう。
我が子の行動や言動に対して、心配な気持ちや不安な気持ちを持つかもしれませんが、我が子にとって
一番の味方であり、信じることが大切になります。
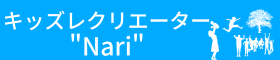

コメント